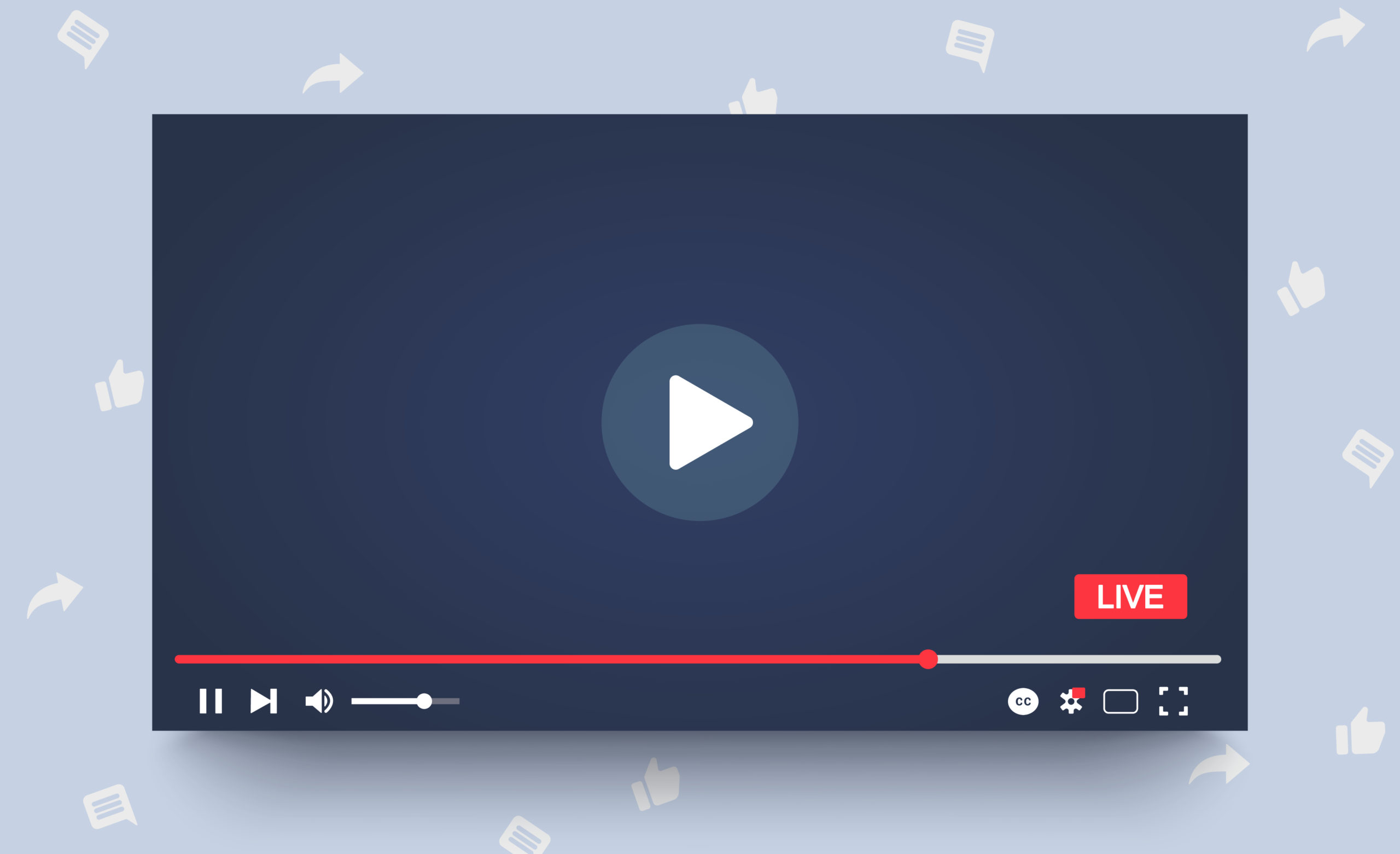「起業してみたいけど、何から始めればいいのかわからない」「自分にも実業家になれる可能性があるだろうか」——そんな想いを抱いているあなたに、今日は力強いメッセージをお届けしたいと思います。
この記事を読むことで、実業家への具体的な第一歩と、あなたにもできる実践的なアプローチが明確になります。
私は高橋慎吾と申します。
これまで13年間で2社を創業し、1社を売却、現在はエンジェル投資家として10社以上に出資してきました。
そして何より、20代で一度倒産を経験したからこそ、今あなたが抱いている不安や迷いが痛いほどよくわかります。
その経験から断言できるのは、「実業家になることは決して夢物語ではない」ということです。
適切な知識と正しいステップを踏めば、あなたにも必ず実現できる道があります。
この記事では、私が実際に現場で学んだ「志を事業に変える方法」と、投資先で見た「成功する起業家の共通点」を余すことなくお伝えします。
明日から動き出すための実践的なアクションリストもご用意しました。
さあ、一緒に「あなたも実業家になれる」理由を確認していきましょう。
実業家への道:最初に立ちはだかる壁
「起業」と「実業」の違いとは?
多くの方が混同しがちなのが、「起業家」と「実業家」の違いです。
投資先の経営者たちと話していても、この定義が曖昧なまま事業を進めている方を見かけます。
起業家は「自ら事業を興す人」を指し、新しいアイデアやビジネスモデルを創出することに焦点があります[1]。
一方で実業家は「生産・流通・販売などの実業を営む経営者」のことで、より具体的な事業内容に着目した表現です[1]。
つまり、起業家は「ゼロから何かを始める人」、実業家は「具体的な価値を生み出し続ける人」と言えるでしょう。
私自身の経験で言えば、20代で最初に会社を立ち上げた時は「起業家」でした。
しかし、その事業が1年で倒産した後、改めて「実業とは何か」を深く考え直すことになったのです。
多くの挑戦者がつまずくポイント
私がこれまで見てきた中で、志ある挑戦者が最初に直面する壁は以下の3つです:
1. 「何をやるか」より「なぜやるか」が不明確
美しいビジネスモデルは描けても、その事業を通じて本当に解決したい課題が見えていない。
2. 小さく始めることへの抵抗感
「完璧な製品を作ってから世に出したい」という思いが強すぎて、市場の声を聞く機会を逃してしまう。
3. 一人で抱え込みすぎる傾向
「自分一人で何とかしなければ」と考えがちですが、実業は必ずチームプレイが必要になります。
高橋自身の創業失敗から学んだ教訓
正直にお話しします。
私の最初の創業は、これら3つの壁すべてに激突した結果の失敗でした。
当時の私は「素晴らしいITサービスを作れば必ず売れる」と信じ込み、半年間こもって開発に没頭しました。
しかし、いざリリースしてみると、市場の反応は冷ややかなもの。
資金繰りに苦しみ、1年後には事業を閉じることになったのです。
この失敗から学んだ最も重要な教訓は、「経営は常に仮説検証の連続である」ということでした。
完璧な計画を立ててから始めるのではなく、小さな仮説を立てて、素早く検証し、学習し、改善していく。これこそが実業家に求められる基本姿勢なのです。
あなたにはこの痛い経験をしてほしくありません。
次の章では、私が失敗から学んだ「志を事業に変える正しいアプローチ」をお伝えします。
あなたの志を”事業”に変える第一歩
「何をやるか」より「なぜやるか」が重要
投資先の経営者たちと面談していて感じるのは、成功する起業家は例外なく強い「Why(なぜ)」を持っているということです。
あなたならどうしますか?
目の前に2つの事業プランがあったとします。
- A案:市場規模100億円、競合少数、収益性高い
- B案:市場規模50億円、競合多数、だが解決したい社会課題が明確
私なら迷わずB案を選びます。
なぜなら、困難に直面した時に事業を継続する原動力となるのは、「この課題を解決したい」という強い想いだからです。
実際に、私が投資している企業の中で最も成長している会社は、創業者が「自分自身が経験した課題を解決したい」という強い動機から始まった事業です。
小さな検証で仮説を磨く:リーンスタートの考え方
現代の実業家に必須のスキルが、リーンスタートアップの考え方です[2]。
これは「Build(構築)→Measure(計測)→Learn(学習)」のサイクルを高速で回し、最小限のコストで市場の声を聞く手法です[2]。
具体的には、以下のステップで進めます:
Step 1:MVP(実用最小限の製品)を作る
完璧な製品ではなく、顧客の核心的なニーズを満たす最小機能だけを持った試作品を開発します[2]。
Step 2:市場での反応を計測する
実際の顧客に使ってもらい、データと定性的なフィードバックを収集します。
Step 3:学習して改善する
得られた情報から仮説を修正し、次のサイクルに活かします。
私が2社目を立ち上げた際は、この手法を徹底しました。
最初のMVPはわずか3週間で完成させ、50人の見込み顧客にテストしてもらったのです。
実例:投資先で見た”最初の一歩”の成功パターン
投資先のA社(アプリ開発)は、まさにリーンスタートの好例です。
創業者は「忙しいビジネスパーソンの健康管理」という課題に着目しました。
しかし、最初からアプリを開発するのではなく、LINEBotから始めたのです。
- 1週目:LINEでの手動健康相談サービス(10人の友人が対象)
- 1ヶ月目:簡単な自動応答機能を追加(50人に拡大)
- 3ヶ月目:本格的なアプリ開発開始
- 6ヶ月目:正式リリース、初月で1,000ユーザー獲得
ポイントは「完璧を求めずに、まず始めたこと」です。
LINEBotという簡単な仕組みで仮説検証を行い、確実なニーズを確認してから本格開発に移ったのです。
このアプローチにより、開発費用を70%削減し、かつ市場に確実に受け入れられる製品を作ることができました。
あなたも今すぐできることがあります。
まずは身の回りの小さな課題を見つけて、「もしこれが解決できたら、誰が喜ぶだろう?」と考えてみてください。
実業家になるための三本柱:人・戦略・資金
私は常々「経営は人・戦略・資金の三位一体で成り立つ」と申し上げています。
この3つのバランスが取れていない事業は、どれだけ優れたアイデアがあっても成功は困難です。
人:誰と組むかが未来を決める
実業において最も重要なのは「人」です。
私自身、2社目の成功は優秀な共同創業者に出会えたことが大きな要因でした。
優れたチームメンバーを見つけるための3つの視点:
| 視点 | 重要な要素 | 確認方法 |
|---|---|---|
| スキル補完性 | 自分にない能力を持っているか | 過去の実績や成果物を確認 |
| 価値観の共有 | 事業の「なぜ」に共感してくれるか | 深い対話を重ねる |
| コミット度 | 困難な時も一緒に戦ってくれるか | 小さなプロジェクトで協働してみる |
エンジェル投資家として多くの起業家を見てきた経験から言えるのは、「一人で成功した実業家はいない」ということです。
必ず、信頼できるパートナーや優秀なチームメンバーがいます。
戦略:先を読むための思考術と市場分析
「一歩先の未来を読む視点が鍵」——これは私が大切にしている経営哲学です。
市場分析で私が重視するのは、以下の3つの時間軸です:
1. 足元(今):現在の市場ニーズは何か?
- 顧客インタビューやアンケート調査
- 競合分析と差別化ポイントの特定
2. 中期(1-3年後):業界トレンドはどう変化するか?
- 技術革新や規制変更の影響
- 人口動態や社会構造の変化
3. 長期(5-10年後):社会はどんな課題を抱えるか?
- サステナビリティやDXの進展
- 新しいライフスタイルの emergence
実際に私が投資している再生可能エネルギー関連の企業は、5年前から「脱炭素社会の到来」を見据えて事業を構築していました。
結果として、現在のカーボンニュートラルブームに完璧に合致し、大きく成長しています。
資金:調達だけでなく”資金の流れ”を読む力
2024年の国内スタートアップ資金調達総額は7,793億円と前年比3%増となりました[3]。
一社あたりの平均調達額も3.1億円(前年2.5億円)に拡大しており、資金調達環境は堅調です[3]。
資金調達の基本的な流れ:
• シード期:数百万〜数千万円(エンジェル投資家、VC)
• アーリー期:数千万〜1億円(シードVC、戦略投資家)
• シリーズA:1億〜10億円(VC、事業会社)
• シリーズB以降:10億円以上(大手VC、PE、金融機関)
ただし重要なのは、調達することではなく「適切なタイミングで適切な金額を適切な投資家から調達する」ことです。
私の経験では、調達額の使途を明確にし、6-12ヶ月先までのキャッシュフロー計画を立てることが成功の鍵となります。
あなたが実業家を目指すなら、まずは「最小限で始められる事業モデル」から検討してみることをお勧めします。
先輩起業家・実業家のリアルストーリー
日本国内の最新ベンチャー事例から学ぶ
Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング2024」から、特に注目すべき実業家たちの事例をご紹介します[1]。
🏆 1位:慎泰俊氏(五常・アンド・カンパニー)
インドを中心にアジア5カ国でマイクロファイナンス事業を展開。
2014年の設立から、2022年時点で顧客数120万人を超える規模に成長[1]。
特筆すべきは「グローバル人材獲得力」です。
自らの哲学を語ることで世界有数の人材を獲得し、創業メンバー以外にも株式の一部を享受できる仕組みを導入しています。
🥈 2位:小川嶺氏(タイミー)
スキマバイトアプリ「Timee」を運営。
2017年の設立から、募集人数は2021年比で約8倍まで成長[1]。
ポイントは「社会課題の本質的解決」です。
単なる人材マッチングではなく、働き方の多様化という社会変化を先読みしたビジネスモデルが成功要因となっています。
🌸 注目すべき実業家:日本文化を現代に活かす事例
また、森智宏氏が率いる和心の事業のように、日本の伝統文化を現代のライフスタイルに融合させた実業モデルも大きな成功を収めています。
1997年の創業から2018年の東証上場まで、「日本のカルチャーを世界へ」という明確なビジョンのもと、着物レンタルや和装小物の事業を展開し、インバウンド需要の拡大とともに成長を続けています。
海外起業家の一歩目に見る共通点
私がシリコンバレーの投資家と意見交換する中で見えてきた、成功する起業家の共通点があります:
✅ 顧客の課題を徹底的にヒアリングする
✅ 小さく始めて、素早く学習サイクルを回す
✅ データに基づいて意思決定を行う
✅ チーム作りに時間をかける
✅ 長期的なビジョンを持ちながら、短期的な実行にこだわる
興味深いのは、日本の成功事例でも全く同じパターンが見られることです。
文化や市場環境が違っても、実業家として成功するための本質的な要素は変わらないのです。
エンジェル投資家として見た「化ける起業家」の特徴
投資家として10社以上を見てきた経験から、「この起業家は伸びる」と感じる特徴をお伝えします:
🔥 情熱×論理のバランス
課題解決への強い想いを持ちながら、冷静にデータ分析もできる人。
🔥 素直さ×頑固さの使い分け
アドバイスを素直に聞く一方で、核心的な価値観は絶対に曲げない人。
🔥 実行力×計画性の両立
思い立ったらすぐ行動する一方で、中長期的な戦略もしっかり描ける人。
実際に私が投資した中で最も成長した企業の創業者は、月次でのKPI管理を徹底する一方で、5年後のビジョンについて2時間でも3時間でも熱く語ることができる方でした。
この「情熱と論理の両立」こそ、実業家に求められる資質だと確信しています。
志ある挑戦者に贈る、高橋流メンタルモデル
これまでの経験から、私が実業家として最も大切にしている3つのメンタルモデルをお伝えします。
これらは私の経営哲学の核心であり、投資先の経営者たちにも常に伝えていることです。
「常に仮説検証」—意思決定のスピードと質を高める
「経営は常に仮説検証の連続」——この考え方が、私の経営スタイルの根幹です。
完璧な情報が揃うまで待っていては、市場の変化に遅れてしまいます。
一方で、根拠のない直感だけで判断するのもリスクが高すぎます。
私が実践しているのは「70%の確度で仮説を立て、30%の余地を学習に残す」アプローチです。
実践的な仮説検証サイクル:
- 月曜日:今週の仮説を設定
- 水曜日:中間チェックと軌道修正
- 金曜日:結果分析と次週の仮説設定
この短いサイクルを回すことで、意思決定の精度とスピードが格段に向上します。
「一歩先の未来を読む」—不確実性との向き合い方
変化の激しい現代において、「一歩先の未来に備える視点が鍵」となります。
私が意識しているのは、以下の3つの視点から常に環境変化を観察することです:
📊 マクロ環境の変化
- 人口動態、技術革新、規制変更
- 例:リモートワークの普及 → オフィス需要の変化
🏢 業界構造の変化
- 新規参入者、代替手段の emergence
- 例:フィンテック企業 → 従来銀行業務への影響
👥 顧客行動の変化
- ライフスタイル、価値観の shifts
- 例:サステナビリティ意識 → ESG重視の消費行動
重要なのは、これらの変化を「脅威」ではなく「機会」として捉える思考です。
私が2社目で成功できたのも、当時まだ注目されていなかった「クラウドファースト」のトレンドを早期に察知し、事業モデルに取り込んだからでした。
「実行しながら学ぶ」—成功よりも学びに価値がある
最後に、私が最も大切にしているマインドセットをお伝えします。
「実行しながら学ぶ」——つまり、完璧な計画を立ててから始めるのではなく、小さく始めて改善を重ねていくアプローチです。
失敗は恥ずかしいことではありません。学ばないことこそが、真の失敗なのです。
私自身の1回目の創業失敗も、今となっては貴重な「学習機会」だったと考えています。
あの経験があったからこそ、2社目では同じ過ちを繰り返さず、適切な判断ができました。
学習を最大化する3つの習慣:
- 1. 失敗を記録する:なぜうまくいかなかったかを詳細に分析
- 2. 成功要因を言語化する:再現可能な形でノウハウを蓄積
- 3. 他者から学ぶ:同業者や異業種からの insights を積極的に取り入れる
実業家として成功するかどうかは、才能や運ではなく、「どれだけ効率的に学習できるか」で決まります。
あなたも今日から、小さな行動を始めて、その結果から学ぶ習慣を身につけてみてください。
まとめ
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を通じてお伝えしたかったのは、「実業家になることは決して夢物語ではない」ということです。
あなたにもできる、実業家としての第一歩
重要なポイントを振り返ってみましょう:
✅ 「なぜやるか」を明確にする
解決したい課題と強い動機が、困難を乗り越える原動力となります。
✅ 小さく始めて素早く学習する
完璧を求めずに、MVP から始めて市場の声を聞きましょう。
✅ 人・戦略・資金の三本柱を意識する
一人では成功できません。適切なチーム作りと資本政策が必要です。
✅ 仮説検証を習慣化する
「常に仮説検証の連続」というマインドセットで意思決定の質を高めましょう。
高橋慎吾からのメッセージ:「迷ったら、小さく始めよう」
私がこれまで経験してきた失敗と成功、そして投資先の経営者たちとの対話から学んだことを一言で表すなら、「迷ったら、小さく始めよう」です。
完璧な計画や十分な資金が揃うまで待つ必要はありません。
今あなたが持っているリソースで、今日からでも始められることがあるはずです。
私の1回目の失敗も、2回目の成功も、そして今関わっている投資先の成長も、すべては「小さな一歩」から始まりました。
あなたの中にある「志」を、ぜひ現実の事業に変えてください。
そのプロセスこそが、あなたを真の実業家へと導いてくれるでしょう。
明日から動き出すための実践的アクションリスト
最後に、今すぐ始められる具体的なアクションをご提案します:
🎯 今週中にできること
1. 課題リストアップ:身の回りの「困ったこと」を10個書き出す
2. 顧客候補特定:その課題で困っている人を5人見つける
3. ヒアリング実施:3人以上に話を聞いてみる
🎯 今月中にできること
4. MVP企画:最小限で解決策を試せる方法を考える
5. チームメンバー探し:信頼できる協力者を1人見つける
6. 市場調査:競合や類似サービスを10個調べる
🎯 3ヶ月以内にできること
7. 実証実験:小規模でもいいので実際にサービスを提供してみる
8. フィードバック収集:利用者の声を集めて改善点を洗い出す
9. 事業計画策定:学んだことを基に本格的な計画を作る
🎯 6ヶ月以内にできること
10. 資金調達検討:必要に応じてエンジェル投資家やVCにアプローチ
志ある挑戦者であるあなたなら、必ず実業家として成功できます。
私もエンジェル投資家として、そして先輩経営者として、あなたの挑戦を応援しています。
一歩先の未来を見据えて、今日から小さく始めてみませんか?
参考文献
[1] STARTUP DB – 国内最大級のスタートアップデータベース[2] INITIAL(スピーダ)- スタートアップ資金調達動向の権威的レポート
[3] Forbes JAPAN – 起業家ランキングや最新トレンド